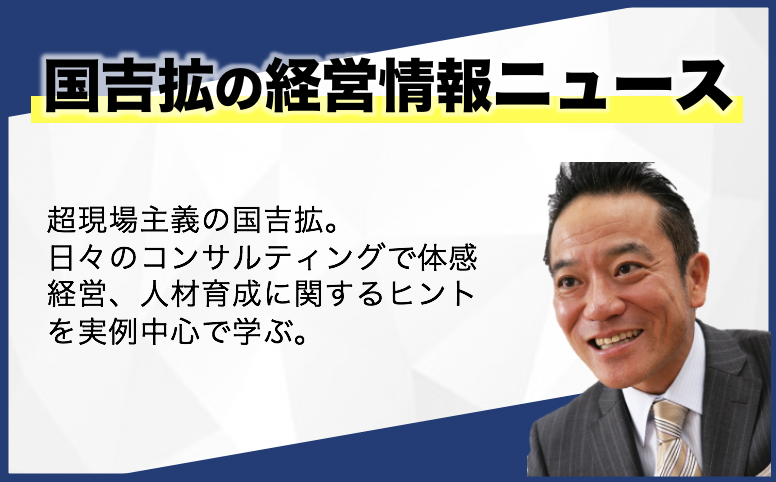◆新年、全体会議での一コマ
新たな年を迎えるこの時期は目標を設定する絶好のタイミングです。昨年、様ざまな理由(言い訳)で実践することができなかった取り組みも「今年こそは」という想いで、目標設定をした方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今回はある会社の新年の全体会議のエピソードを紹介します。この会議は、普段各拠点に分かれて仕事をしている全社員が一同に集います。会社としての方針を共有し、ベクトルを合わせ、モチベーションを高める重要な場です。その席では、毎年恒例のことですが、一人ずつ今年の目標を発表します。ある営業マンが、「今年はお客様から絶対の信頼を勝ち取ります。」、「ライバルに負けない営業をします!」「個人の成績を躍進させます。」間接部門の方も「ムダを省き、生産性を向上させます。」、など、力強く抱負を述べます。どれも素晴らしいコメントで、発表のたびに会場は拍手喝采。社長も「頑張ってください」、と一人ひとりに声かけを行いました。私も頼もしくその光景を見ていましたが、若干モヤモヤした感情が沸き上がってきました。それは、抱負(目標)が具体的でないからです。12月になり、新年に立てた抱負を振り返ったとき、「達成できた、できなかった」はどのように判断をすれば良いのでしょうか。「お客様からの信頼を勝ち取る」では客観的な評価ができません。客観的な評価は「数字」でしか判断できないのです。日頃から会話の中でも常に「数字」を取り入れる。また、あいまいな表現を全て「数値化」していく。「数字」に強い部下を育てていくことが、利益を産む体質をつくり、個人・組織の成長につながっていくのです。
◆目標へのこだわりとは、目標・現状・差額が頭に入っていること
ご支援先の営業会議の現場での事例です。「先月の目標と実績、達成率を教えてください」毎月目標を達成しているAさんは、「はい、先月の売上目標500万円に対して実績が550万。達成率110%です」と即答。かたや、年間で言うと3勝9敗。目標未達の月の方が多いBさんは、「いくらでしたっけ。多分、達成していたと思います」実績を見てみると、目標500万円に対し、492万円でギリギリ未達。良いところまで行っているのですが、あと一歩届かないという月が非常に多いのです。これは目標に対しこだわりがないのももちろんのことですが、そもそも、数字に対して非常に鈍感であることが大きな理由です。また、Bさんのような営業は利益率に対する意識も非常に弱いのも共通しています。「先月の粗利率は何%でしたか?」と質問をしても「まあまあです」との回答。この商品の原価はいくら?」と聞いても即答できません。これでは利益を確保することは難しいです。
◆ものごとを「数値化」してとらえよう
「数値化」とは抽象的、主観的であいまいな状態を、数字を使うことであいまいさを排除し、客観的な情報に変換することです。数値化を行うことは2つのメリットがあります。それが、①自身、組織に何が足りないのか、どういう課題があるのかを「見える化」できるということ。②認識のズレがなくなり、双方の納得感・公平性が生まれるということ、です。 ビジネスの現場は全て、「数値化」できるといっても過言ではありません。先の新年の抱負であれば、「成績を躍進させます」ではなく、「対目標130%を目指します」に変換。「生産性を向上させます」ではなく、「残業時間を昨年と比較し、半分を目指し、生産性を向上させます」など、具体的目標に修正すべきです。
◆数 字 に 強 い 部 下 を 育 て る た め の ポ イ ン ト
それでは、数字に強い部下を育てるためには何に注意する必要がありますでしょうか。それが次の通りです。
①会話の中に具体的な数字を使う
ちょっとで目標達成です」といった抽象的な言葉を使っていませんか?今後、そのような会話はやめてください。「今月は目標まであと130万円」とか、「この商品は、23%の粗利益率を確保してください」というように、会話に具体的な数字を入れることで、部下の数字に対する意識が非常に高まってきます。これはビジネスの現場以外でも同様です。「半年間ダイエットを頑張る」ではなく「半年間で5キロ減をダイエットの目標とする」など日頃から具体的な数字を入れることで数字に強い人材になっていきます。
②グラフ、表の貼りだし
アナログな手法ではありますが、組織、個人の目標と現状を営業所の壁に貼りだすことも効果的です。競争意欲が生まれると同時に、数字に対する苦手意識があるメンバーも現状を瞬時に把握することができます。
③量からしか質は生まれない(確率論に逃げない)
求めてはいけません。なぜならば、成功のウラにはそれを超える失敗の数も存在しますし、また、極端な事例ですが、前年比500%の利益伸長といってもそもそも前年が1万円の利益などあまりにも母数が小さければ、その伸長率も評価できるものではないからです。ベースとなる行動量があってこその確率論なのです。
④簡単なビジネス数字はレクチャーする
損益計算書・貸借対照表の読み方を指導したことはありますか?日頃から自社、他社の決算書を読みこむことで、利益の重要性が理解できるようになります。しかしながら、レクチャーできるほどの知識を自分が持っていなければ元も子もありませんので、まずは自分自身が数字に強くなることも重要です。
【ポイント】
数字のない議論はただのお遊びであり、机上の空論です。日頃からできる限り数字を根拠とした仕事をしていくことが組織・個人の成長につながっていきます。
株式会社経営支援センター チーフコンサルタント 吉田 敬真